Clinical & Research Activity








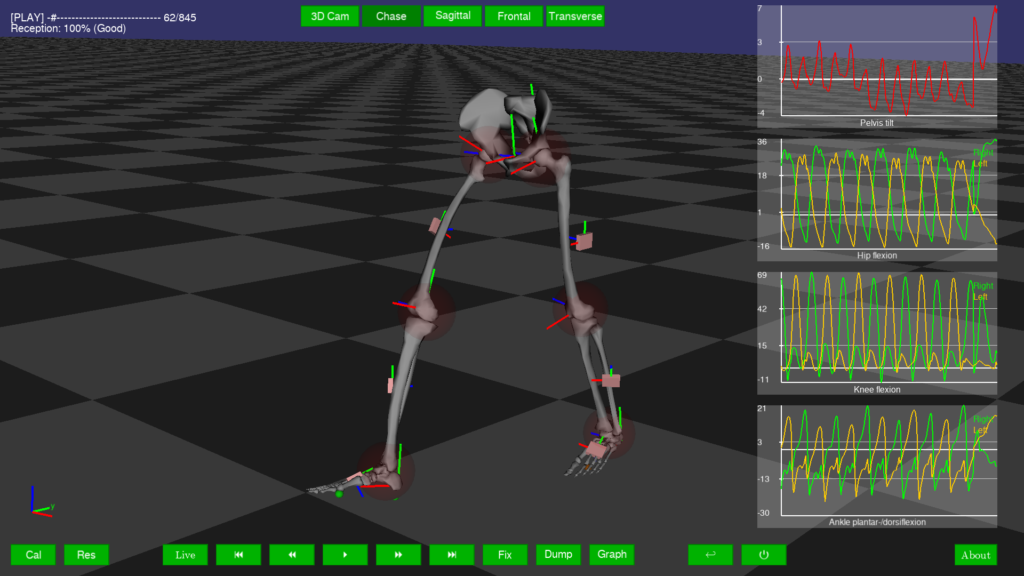
e-skin MEVA:7個のIMUセンサを搭載した専用スパッツを装着するだけで、カメラ不要で場所を限らず計測が可能。運動指導のフィードバックとして臨床で活用したり、疾患特有の歩行特性を分析するなどの研究にも用いています。





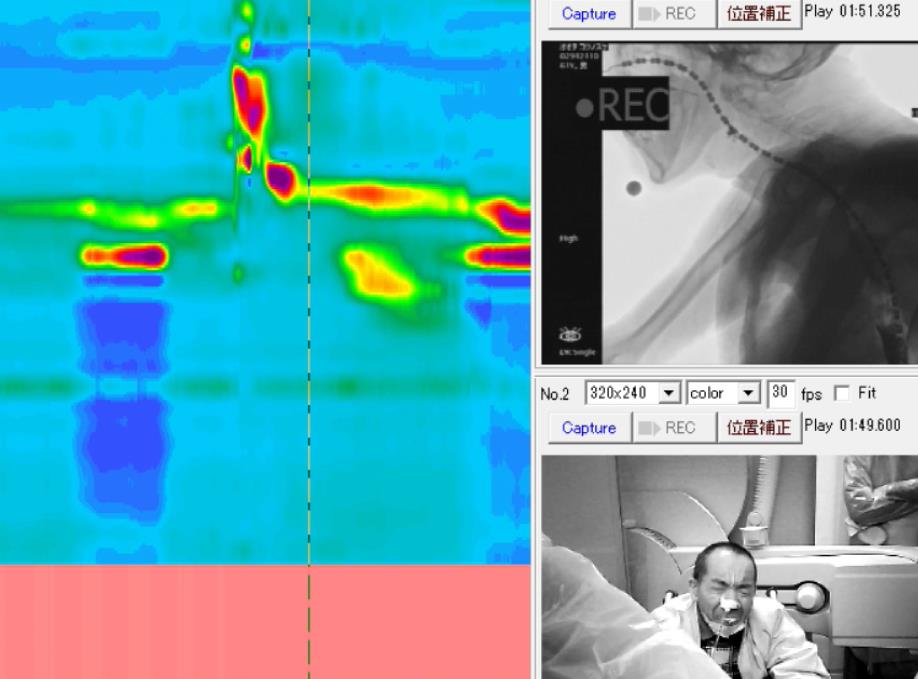

Clinical



附属病院
付属
病院
千葉北総病院
武蔵小杉病院
多摩永山病院
合
計
理学
療法士
29
22
13
11
75
作業
療法士
12
9
4
4
29
言語
聴覚士
6
5
3
4
18
臨床
心理士
0
3
0
0
3
合計
47
36
20
19
122
入院
外来